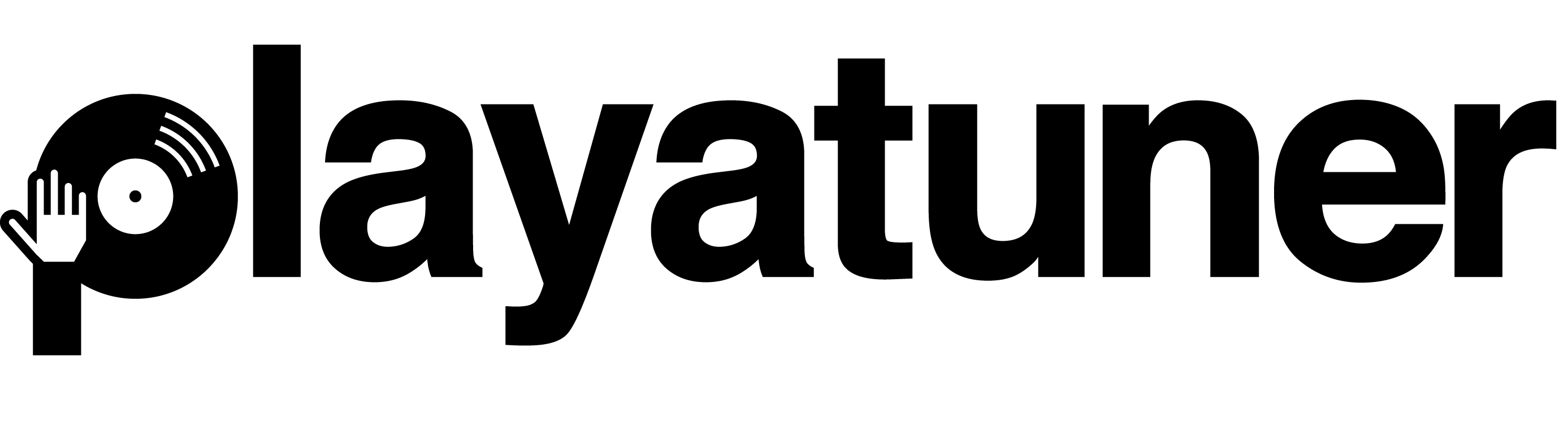複数のヒップホップ世界線をクロスオーバーするアーティストから学ぶ。「最も危険なドラマー」Chris Daveとヒップホップ。
ヒップホップ
に深く関わりのあるミュージシャン/演奏者と言ったら誰を思い浮かべるだろうか?恐らくこのお題であれば、大半の人がThe RootsのQuestloveを思い浮かべるだろう。彼がヒップホップに及ぼした影響は大きく、The Rootsと彼がいなければ、生演奏とヒップホップは今でも溝があったかもしれない。J DillaとQuestloveとD’Angeloがいなければ、多くの音楽が生まれていなかったであろう。
そんなQuestloveが「最も危険なドラマー」と呼んでいるドラマーがいることをご存知だろうか?恐らくヒップホップ/ジャズ/ソウルを演奏する側のミュージシャンであれば、Chris Dave(クリス・デイヴ)のことは知っているだろう。彼はヒップホップ/ジャズにおいて非常に重要な役割と担っているドラマー/ビートメーカーである。Jazz the New Chapterなどの本で、既にこの記事の内容に近いものは何度もカバーされているかも知れないが、今一度あまりこの辺を聞かない「ヒップホップファン」に届けるため、ヒップホップマガジンとしての観点を書きたい。普段はアーティストやラッパーの想いを書くことが多いが、ヒップホップのサブジャンルが多様化するなかで、プレイヤーとヒップホップの繋がりに注目を当てることも非常に重要であると感じる。今回は入門としてChris Daveという存在を紹介しつつ、プレイヤーとラッパーの繋がりや、クロスオーバーの重要性について考えたい。
そんなChris Daveはドラマーとして最も大きな影響はジャズだと語っているが、彼のキャリアはR&BバンドのMint Conditionのドラマーを務めたことからはじまった。彼は実際にはJ Dillaと同世代であるが、彼がJ Dillaから受けた影響は計り知れない。彼のキャリアの説明は端折るが、彼はD’Angelo & The Vanguard、ミシェル・ンデゲオチェロ、ロバート・グラスパー・エクスペリメント、エリカ・バドゥ等、そしてアデル、エド・シーラン、ジャスティン・ビーバーなどのポップスターの作品にも参加している。さらには2017年末に宇多田ヒカルの「あなた」に参加し、ブラックミュージックの垣根を超え、様々なジャンルにクロスオーバーしている。
そんなドラマー/ビートメーカーChris Daveであるが、彼の待望のソロ・アルバムとなる「Chris Dave and The Drumhedz」が1月26日に発売となる。演奏メンバーはD’Angelo & The Vanguardでもおなじみのピノ・パラディーノ(B)、アイザイア・シャーキー(G)の他に、ロバート・グラスパー、ケイシー・ベンジャミン、エミネムやビヨンセのトランペットを務めたキーヨン・ハロルドなどが参加しており、最も熱いミュージシャンたちが集まっている。そんなアルバムのリード曲となる「Black Hole」ではAnderson .Paakがボーカルを務めているので、要チェックだ。
このアルバムには他にもスラム・ヴィレッジのElzhi、Little BrotherのPhonte、TDEのSiR、Bilal、Anna Wiseなどが参加しており、確実にヒップホップファンの心を掴む作品となっている。彼はドラマーとしてだけではなく、「ビートメーカー」としてトップレベルのヒップホップアーティストから高いを評価を受けている。
ヒップホップと生演奏サイクルとChris Dave
彼は今作を含め今までに複数のヒップホップアーティストと共演をしているが、彼のヒップホップとの繋がりはそこだけではない。彼は「プレイヤー」という観点で、ヒップホップの一つの形として最前線にいるのだ。ヒップホップの「サウンドの本質」は音楽と知識のサイクルであると言えるなか、彼はそのサイクルの先端にいる。元々ヒップホップは楽器を持っていなかった人たちがレコードプレーヤーと言葉を使い「アーティスト」になれる土台を作ったと私は解釈している。なので影響するよりも、他のジャンルを飲み込むという形で影響されることが多かったジャンルだったと解釈することもできるが、音楽と知識のサイクルが回るにつれ、逆に他のジャンルを影響することが増えたのだ。その「飲み込み」がジャンルの境界線を薄めた形となる。
その一例がJ DillaのMPC打ち込みなどを生演奏で再現することであろう。昔はクライド・スタブルフィールドのドラミングを再現するように打ち込んだプロデューサーたちは多かったが、J Dillaのクオンタイズされていないビート感は数多くのミュージシャンの興味の対象となった。そこでD’Angeloのようなアーティストも出てき、Questloveのようなドラマーを影響したことがきっかけで、ヒップホップと生演奏というものが今まで以上に密接になった。MPCやエンソニックのようなリズムマシンにて起こる微妙なレイテンシーなどを逆に生演奏で昇華し、様々な手法とかけ合わせる流れの最先端がChris DaveやNate Smithのようなドラマーであると言われている。ジャズ/ファンク/ソウルなど様々なジャンルを飲み込んだヒップホップが一周周り、ゴスペルやジャズドラマーの元に戻ってくるサイクルはある意味凄く「ヒップホップ的」であると感じる。ジャズ界隈の方からすると、ごく当たり前の話であるかも知れないが、Chris Daveなどの「プレイヤー」は世間的に有名な「ヒップホップ」をフォローしているヒップホップファンからは案外知られていないと感じる。
実際に彼のヒップホップとの密接な関係は、バンド活動以外でも見ることができる。実はChris Daveはレジェンド・プロデューサーであるリック・ルービンが保有するスタジオShangri-Laのインハウス・ドラマーなのだ。リック・ルービンは彼に多くのアーティストを紹介している。このように多くのヒップホップアーティストが彼を必要としており、ジャズドラマーである彼との還元の相互関係が出来上がっている。
プレイヤーとラッパーの繋がり
Chris Daveもそうだが、実際に「プレイヤー」とヒップホップアーティストが繋がり、キャリアが広まる事例は米国では多い。近年だとThundercatがケンドリック・ラマーとコラボをし、グラミー賞を受賞した。これは直接Thundercatのバンドメンバーから聞いたことなのだが、Thundercatがグラミー受賞してから客層も動員数もガラッと変わったらしい。ケンドリックはThundercatの類まれな演奏/アイディアからインスピレーションを受け、Thundercatはラッパーと作業するのが苦手であったが、ケンドリックから今までリーチできなかった客層とプラットフォームをゲットした。テラス・マーティン、カマシ・ワシントンに関しても同じような効果を見ることができたのではないだろうか。ジョージ・クリントンに関しては若い世代が入るきっかけになったと言えるだろう。このような相互関係が音楽の「サイクル」を次のレベルに持ち上げることであるように感じる。TPABでジャズやファンクに興味を持った人も多く、これもヒップホップの礎となったジャズやファンクに対する「還元」になっており、音楽業界の底上げになったと言っても過言ではない作品だ。逆にChris Daveのデビューアルバムとなる「Chris Dave and The Drumhedz」では、Anderson .Paakは「毎日を生き抜くハスラーとして陥る闇」についてラップしており、サウンド以外のヒップホップ面も取り入れている。Little BrotherのPhonteとSlum VillageのElzhiをフィーチャリングした楽曲もオススメであり、演奏者側がヒップホップにハマるきっかけにもなる。
上記の例や、クリス・デイヴがいかにヒップホップを含めた多くの音楽を昇華したかを考えると、このような「ヒップホップアーティスト」×「ヒップホップ演奏者」のコラボがいかに重要かがわかる。それは「音楽」として同じ祖を持っているが、違う「ヒップホップの世界線」で成長してきた人から受けるインスピレーションという意味でもあり、リスナーを相互的に流入し合う意味合いでもある。特に日本の場合は、ラップブームがあるなかで、もしかしたら音楽として成長していくことを考えると、このようなプレイヤーとのコラボというのはさらに重要になってくるのではないだろうか。
これは韻シストをインタビューしたときにも彼らが語っていたことなのだが、上記のような「バンドマン/ミュージシャン」としての大きな存在がいるのもあり、現在の世の中では「ヒップホップの影響は絶対外せない世代のミュージシャン」が多く存在している。演奏面でヒップホップを聞いている人と、文化としてヒップホップをフォローしている人では、生きる「ヒップホップの世界線」は全く違うかも知れないが、そんなアーティストたちのコラボがこれから日本でも頻繁に起こると予想ができる。そしてケンドリックやJay-Zがやったように、ヒップホップがリードをして、多くのプレイヤーが繁栄する世の中になると、マイナーなジャンルにとっては素晴らしい結果となるかもしれない。
日本では宇多田ヒカルがChris Daveにオファーをし、コラボに至ったが、日本のヒップホップ内でもこのようなエコシステムが出来上がったらとても面白いと感じる。現に何人かのラッパーが「インディーズ・バンドマン」であったアーティストと組んで作品を出しているが、今後はもっと増えるだろう。そして「Chris Dave and The Drumhedz」はそんな「ヒップホップの複数の世界線」をクロスオーバーするコラボをさらに促す作品となるだろう。
いいね!して、ちょっと「濃い」
ヒップホップ記事をチェック!